看護師として、保育の現場で広げるアタッチメントの輪
「赤ちゃんとお母さんが笑顔でいられる時間を増やしたい」ーそう話すのは、名古屋市の保育園に勤務し、看護師として20年近く子どもたちを見守り続けてきた山田友子さん。医療現場から保育の世界に飛び込み、日本アタッチメント育児協会のベビーマッサージインストラクター資格を活かして活動するようになった経緯を伺いました。
医療から保育の世界へ

現在、山田さんは看護師として保育園で、保健業務と保育の両方を担当しています。医療機関での勤務を経て、公立保育園の嘱託職員として保育の現場に入ったことが、保育との最初の出会いでした。その後は小児科や乳児院でも勤務し、子どもと関わる現場を幅広く経験。現在の園には15年ほど勤めており、保育に携わるようになっておよそ20年が経ちます。
「保育士の資格を持っていない分、必死で勉強しました」と山田さんは振り返ります。勤務後の夜遅くまで資料を開き、年間計画づくりの打ち合わせにも保育士に混ざって参加し、何年も現場で学びを積み重ねてきました。
皮膚科勤務の経験から生まれたベビーマッサージへの関心
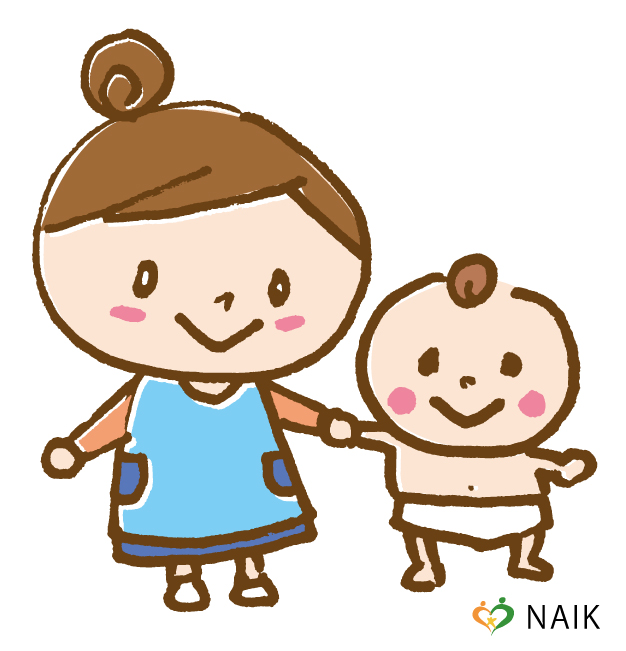
山田さんが日本アタッチメント育児協会と出会ったのは2013年。勤務先の保育園に併設された子育て支援センターで、「自分にできることを探したい」と思っていた時期のことでした。
その頃、ふと頭に浮かんだのは、かつて皮膚科に勤めていた頃の光景でした。アトピーのお子さんを連れたお母さんたちの表情が、来院のたびに少しずつ曇っていく姿を何度も目にしました。薬を塗る、保湿をするという日々のケアが、いつの間にか「やらなければならない義務」になってしまい、親子ともに疲れ切ってしまう現実。「同じケアをするなら、少しでもお母さんと子どもが笑顔になれる時間にできないか。」そう考えるようになったことが、ベビーマッサージを学ぼうと思ったきっかけでした。
その思いを園長に相談したところ、「アタッチメントを大切にする講座がいいのでは」と勧められ、日本アタッチメント育児協会の講座を受講することに。学びの中で、「愛着形成こそが子どもの成長の土台である」という考えに深く共感しました。乳児院での経験からも、触れ合いの大切さを実感していた山田さんにとって、アタッチメント・ベビーマッサージの理論と実践が結びついた瞬間でした。
少人数で丁寧に寄り添う、保育現場での実践

現在は、勤務園の子育て支援センターで年に一度、ベビーマッサージ教室を担当。
遊戯室ではなく、あえて小さな部屋で定員5名ほどの少人数制で行います。
「広い部屋だと声が届かない。赤ちゃんとお母さんの距離が近い方が、安心して楽しめるんです。」といいます。
参加者は、名前シールに“さん”ではなく“ちゃん”をつけ、最初に自己紹介をして打ち解け合うところから始まります。マッサージ中は「お子さんがママを見てますね」「いい顔してるね」と、赤ちゃんの反応を丁寧に言葉にしながら進めます。30分ほどの手技のあとは、自然と“ママ同士のおしゃべり”が始まるのだそうです。
学び直しの再受講と実践の広がり
2013年の初受講から11年が経った、2024年、再びベビーマッサージ講座を受講しました。きっかけは、区の大規模イベント「子育て広場」でのブース担当の声がかかった時に、ちょうど日本アタッチメント育児協会の会報誌「アタッチメント・ライフ」で講座リニューアルの案内を見たことでした。「ママたちに新しい知識を届けたい」という思いから、改めて学び直しを決意。
「初受講の時は教えてもらうだけでしたが、今回は実践してから学んだので、先生の言葉の奥にある意味がよくわかりました」と語ります。また、実技試験で作成した「インストラクション企画案」は実践的でとても役にたったといいます。「これを元に計画を立てて、園長に提出をしました。」とエピソードを話してくださいました。 また、再受講された講座内では、他の受講生から“頼れる先輩”として慕われる存在だったそうです。オイル選びや教室運営の悩みなどの質問に、「おうちにあるものを使って大丈夫」「無理に完璧を目指さなくていい」といったアドバイスを送りました。「子どもがじっとしていられない時は、抱っこでもいい。お姉ちゃんがいるなら、お母さんはお姉ちゃんを、私は赤ちゃんを。どの子も満たされるように関わることが大切なんです」と、現場で培った経験をアドバイスされたそうです。
看護師として、“話せる場”をつくる

保育の現場では、日々さまざまな課題を抱えた親子と出会います。育児に行き詰まってヒステリックになってしまうお母さん、発達に不安を抱きつつも認めきれない親御さん…。そうした中で山田さんが心がけているのは、「なんでも話せる土台をつくること」。世間話の延長から「実はちょっと悩んでいて」と相談が出てくることも少なくありません。
「お母さんたちが安心して話せる雰囲気づくりを大切にしています。看護師だからと構えず、まずは世間話から。『この子、遅いですよね』と相談されたときも、“気づきを認めること”を意識しています。」
必要に応じて専門機関への相談を勧めることもありますが、何より重視するのは“お母さん自身の主体性”。「行きなさい、ではなく“そう感じたなら行ってみるのも一つの手ですよね”と伝えています」と話します。
続けることで広がる、インストラクターとしての可能性
最後に、これから資格を取得して活動を始める方々へのメッセージを伺いました。
「すぐに活躍の場がないと感じる方もいるかもしれません。でも、私のように“やってみない?”と声をかけられる日が必ず来ます。地道に続けていれば、誰かが見ています。その時に、笑顔で赤ちゃんとお母さんのために力を尽くせるように、準備しておいてください。」とメッセージをいただきました。
アタッチメント・ベビーマッサージ インストラクター>>
育児セラピスト前期課程(2級)>>
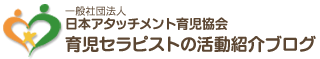
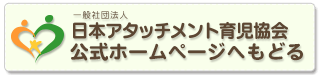
最近のコメント