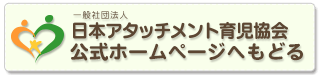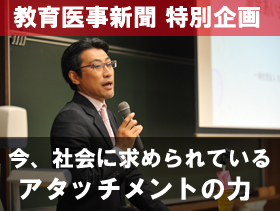恒例!お悩みスーパーバイズ2025
お悩みスーパーバイズ
“保小連携”が現場で機能しないのはなぜ?
保小中一貫校の公立こども園の現場で、小学校に上がると、問題を抱えて不登校になってしまう子が少なからずいます。保育園の時代は、のびのびとしていた園児が、どうして小学校でつまずいてしまうのか、なぜ不登校になってしまうのでしょうか?
オンライン参加の久保田さんからのご質問です。久保田さんは、公立こども園の未満児保育の統括の立場から、“保小連携”に関連したお悩みです。この話は、前提を共有するところから始めないと、つかみどころがないので、前提共有から始めましょう。
文科省の肝いりで始まった「保小連携」は、教育を救うのか?
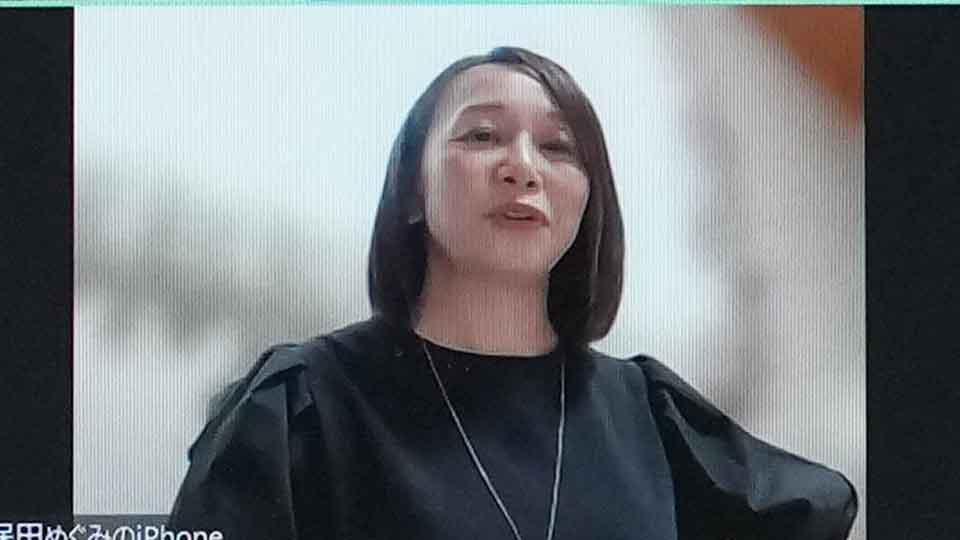
「保小連携」は、幼児教育と小学校教育の円滑な接続を目指す取り組みで、文科省の幼保小の架け橋プログラムなどがあります。
保育所に通う子どもは、比較的緩やかな生活を長時間過ごします。そうした生活から、小学校の授業時間を単位とする教科学習中心の生活にさらされます。その結果、小学校入学後の新しい生活環境に対して戸惑ってしまい、俗にいう「小1プロブレム」に繋がってしまう現状があります。
「小1プロブレム」とは、1年生の学級において、入学後の落ち着かない状態がいつまでも解消されず、教師の話を聞かない、指示通りに行動しない、勝手に授業中に教室の中を立ち歩いたり教室から出て行ったりするなど、授業規律が成立しない状態へと拡大し、こうした状態が数ヵ月にわたって継続する状態をいいます。なかには、そのまま不登校につながってしまう子どもも少なからずいます。
久保田さんのお悩みは、このような背景から生じたものです。
保育士があたりまえに知っているアタッチメントを、
小学校教師は知らない現実

保育園では、アタッチメントを取り入れて、いろいろな個性や特徴をもつ園児に対応しながら、伸び伸びと保育をして、小学校へ送り出します。なかには、発達や、家庭環境が心配な子もいますが、そうでない子どもが、その後、小学校に上がって不登校になっていることを知るケースがいくつもあるそうです。
これは、小学校の先生の知識不足ではありますが、個々の先生の責任ではありません。文科省の描いた青写真の解像度がぼんやりしているため、制度が不完全なのが根本原因だと、わたしは考えています。
アタッチメントも知らない教師が、生徒の家庭環境や生育歴、発達の特徴を考えることもなく、小学一年生の担任をすれば、先生にその気がなくても、追い詰められてしまう生徒は、一定数生じてしまうでしょう。
小学校教師は、全員アタッチメントをしっかり学ぶべき

当協会には、わたしがよく知る小学校教師が2人います。どちらも、本当にすばらしい教師です。そんな彼らが言っていたのは、「アタッチメントを学んで、生徒の問題行動は家庭にあったことに気づかされました。いままでは、子どものことだけを気にかけてきましたが、その後ろの家庭や親にも目を向けなければいけなかった。」ということです。どんなに良い先生でも、知らなければ、それまでです。その無知が、生徒に与える影響は計り知れません。
しかし、これは、教育者を育成するための制度設計の問題に他なりません。それは、一朝一夕に何とかなるものではありません。「保小連携」は、今のところ絵に描いた餅でしかありません。問題は変わらず起きているのがその証拠です。久保田さんの憂いの根っこには、そんな“どうにもならないやるせなさ”があるように思います。
わたしたちが園児にできることは、親にバトンを託すこと

それでも、わたしたちは、現場でできることを探して、実践するしかありません。保育士が、小学校に上がる園児にしてあげられることは何か?小学校への働きかけもできるかもしれませんが、それは制度設計の領域です。
小学校に上がった後も、子どもを守ってあげられるのは親です。親への啓蒙は、子どもにとって、もっとも良い影響をもたらします。「子どもが不登校になったら」に備える啓蒙です。不登校は、どんな子どもに起こり得ます。発達障害で生きづらさを抱える子どもだけに起こることではありません。「学校行きたくない」は、すべての子どもが一度は言うセリフです。そんな誰にもある瞬間を、不登校になるまでこじらせないことが重要です。
「学校行きたくない」に対する魔法の言葉
子どもが「学校行きたくない」と言った時、それが不登校にまで発展してしまうかどうかは、初動(最初の行動・言動)がすべてを握ります。そこで無理に行かせれば、その日は行くかもしれません。しかし、遅かれ早かれ不登校になるでしょう。
最初の「学校行きたくない」に対して、「わかった、いいよ」と言ってあげるのです。そして、その日は、お母さんかお父さんのどちらかが、会社を休んでください。そして、子どものはなしを、一日かけて“聞ききる”ことをしてみてください。
つぎの日、あるいはその次の日、子どもは、みずから学校に行くでしょう。
このことを、保育園にいるときに、「小学校に上がる心構え」として親御さんに啓蒙したら、子どもにとって、こんなに助かることはありません。小学校の先生がイイ先生だろうと、そうではない先生だろうと、家庭で対応できます。



子どもに興味がない親をもつ1歳児に、保育士は何がしてあげられるのか
今年入ってきた園児のお母さんについてです。低体重で生まれた0歳児(現在は1歳2か月)のお母さんなのですが、子どもを後回しにして、自分の都合や方針を優先します。子どもを家に置いて、ランニングに行くとか、食事制限をストイックにおこなって、子どもに影響があるとか、ベビーベッドに子どもを寝かして、泣いていても、となりの部屋に居て放っておく・・・それを悪気なく言います。お母さん自身にも、成育歴に傷があるようです。お子さんは、過敏なところがあり、発達も心配です。このお母さんに、何をしてあげられるのか、どういう言葉かけをすればいいのか、どう対応すればいいのか、わからなくて悩んでいます。
大阪から東京会場に参加いただいたFさんからのご質問です。お聞きする限り、ネグレクト事例と言ってよいケースだと思います。お母さん自身に、母性のスイッチが入らないまま、目の前に子どもが生まれてしまった状態です。Fさんのお話から、お母さん自身が、親から支配されて育ってきた背景があるようです。ひとつ救いなのは、このお母さんは、とても話し好きで、Fさんにも心を開いていて、なんでも話してくれているということです。
アロマザリングで、保育士がお母さんになる
さて、このお悩みに対する解決策ですが、お子さんが現在1歳2か月という乳児期であること、お母さんが、不適切育児である認識がないことを考えあわせると、まずは、このお子さんにできるだけの母性的養育を、保育の中で与えてあげるアロマザリングを施すことでしょう。 未満児クラスで、Fさんを含む3人の保育士で8人の園児を担当しているそうですので、Fさんが、その子に1対1の時間を出来るだけとってあげて、ぜひベビーマッサージをしてあげて欲しいです。そして、その子のメイン担当(特定養育者)として、Fさんがついてあげるようにしてください。そうして、保育園にいる間は、母性的養育を享受できるようにします。
ベビマ沼に引き入れて、「母性スイッチ」をオンにする
しかし、まだ1歳2か月なので、家庭に帰ったあとのことも重要です。そうなると、このお母さんの「母性スイッチ」を何とかして入れてあげる必要が生じます。ここでは、このお母さんが話し好きで、饒舌な方であることを利用しましょう。定期的に、このお母さんと面談の機会を作って、Fさんとお母さんの関係性を作るのです。
そこから「わたしの頼みだから、何も言わずにきいて」と言えるくらいの仲になったら、ベビーマッサージをいっしょにやってもらいます。何度かやっていると、必ずどんなお母さんでも、スイッチが入ります。これは、エビデンスベースドの話しです。
お母さん自身が抱える育ちの傷も癒される

このプロセスをとおして、お母さん自身が抱える育ちの傷も、同時に癒されていくはずです。このお母さんの根っこは、深そうなので、根気強く取り組む必要があるでしょう。この事例は、お子さんの年齢を考えても、保育だけではなく、お母さんを導くという難易度の高い支援が必要だと思います。
目次
- 開会のあいさつ
- 1日目:全国大会スキルアップ講座
- 『キッズマッサージ/アタッチメント・ジム 全面リニューアル』
- 2日目:育児セラピスト全国大会シンポジウム
- 東京家政大学 子ども支援学部 教授 / 特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 副理事長
保坂 遊 先生 - 基調講演「アートと非認知能力の育ち」
- ▼ 優秀実践者発表
- 「志し」をカタチにして、保育園を立ち上げた保育士の物語
- ― 保育 部門 牧野 クルミさん
- 実家の「庭」からはじまった子育て支援の輪
- ― ダイバーシティ部門 衣川 由理さん
- ランチミーティング
- 恒例!お悩みスーパーバイズ2025