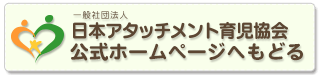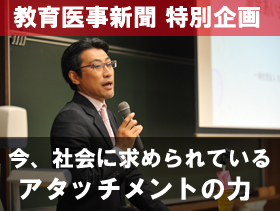全国大会2025優秀実践者発表-「志し」をカタチにして、保育園を立ち上げた保育士の物語 牧野 クルミさん
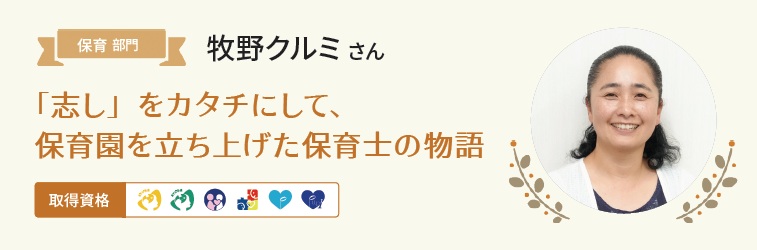
誰でも、いつでも預けられる保育園の実現
牧野さんは、千葉県白井市で小規模保育施設 「葉っぱの家保育園」をみずから立ち上げ、園長として、保育士として、園の運営を行っています。
この園は、「初めての利用でも事前面接なし・ネット予約で当日利用可能で直前予約可能・市外県外でも誰でも使える一時保育」という独自のコンセプトのもと、保育理由を問わない一時保育所を実現しています。
「園児や親御さん、ひいては保育そのものを良くしたい」という熱い思い
保育士歴20年を超える牧野さんは、「葉っぱの家保育園」を立ち上げるまでは、公立園に20年、その後2年ほど私立園に勤務する保育士でした。当協会でも、積極的に学ばれており、熱い思いをもった保育士さんです。
ひとりひとりの園児に合わせた保育をするために、ベビーキッズとプレスクール両方の「あそび発達インストラクター」を取得し、発達障害や発達凸凹による園児の困りごとに寄り添うために、「アタッチメント発達支援アドバイザー」の資格も取得されています。
また、お母さんへの対応や、悩み相談に真摯に対応するために「育児セラピスト1級」を取得し、さらに専門的なカウンセリングを修得するために、「アタッチメント心理カウンセラー」の資格も取得されています。
「園児や親御さん、ひいては保育そのものを良くしたい」という熱い思いを持ち、みずから悩み、工夫し、奮闘する保育士さんであったことを、わたしも当時から記憶しています。全国大会でも、真剣に質問をしてくれて、悩みを相談してくれたのを、今でも覚えています。牧野さんに対するわたしの印象は、まさに「思いの人」です。

「じゃあ、クルミ先生がつくってしまえばいいよ」
そんな牧野さんが、“イチから保育園をつくる” ことを決意したのが、同じ園で働く同僚が言った見出しの一言でした。みずからが勤務する園で、「もっと働く人目線の職場にしよう」と声を上げて奮闘していた時のことだそうです。わたしも、この頃、牧野さんが「職場としての保育園が、もっと変わるべき」と自問自答し、悩んでいたのを見ていました。同僚の方の心の中には、「この園は変わりっこない」という気持ちと、「クルミ先生が理想とする園で働いてみたい」という期待感の両方があったのかもしれません。
「じゃあ、クルミ先生がつくってしまえばいいよ」
この一言が、牧野さんの心にストンと入ったそうです。わたしは、人生には。こういう瞬間が誰しもあると思っています。「できるか、できないか」「損か得か」といった現実を飛び越して、「そうだ、やろう」と素直に思えてしまう瞬間です。牧野さんにとって、このとき機が熟したのだと思います。わたしが、サラリーマンを辞めて、独立起業した時も、まさにこんな瞬間があったことを覚えています。
子育てを助ける園、子どもが主体的に過ごせる園を目指して

「やる」と決めたら走り出してしまう(褒め言葉です)のが、牧野さんです。どんな園を作ろうかと考えた時、みずからが子育てしていた時のことを思い出したそうです。
牧野さんは、21歳、高3,小4の3人子どもを育てる母親でもあります。3人を里帰りも親の手も借りず、夫と2人で育ててきたそうです。それでも、2人だけではどうにもならないことがあります。当時、調べてみてわかったのは、すぐに救いの手を差し伸べてくれる先はないという現実でした。ベビーシッターは家に招き入れることにハードルがある。一時保育を検討するも、面接やら、市への登録やらを乗り越えても、予約競争が激しく、朝から行って並ばなければ予約は取れない。1か月先の予約まで埋まっている。つきつけられたのは、子育ての助けを借りるのは簡単ではない現実でした。
この時みずからが経験した思いから、事前面接なし、予約もネットで完結、直前予約も可の「使いたい時にすぐに利用できる一時保育の園」というメインコンセプトが生まれました。
それと同時に、これまでの20年にわたる保育士経験と、当協会での学びを生かし、「子どもが主体的に活動できる場」という、もう一つの柱となるコンセプトが生まれました。
アタッチメントの学びを活かした保育を実践
こうして、みずからが立ち上げた「葉っぱの家保育園」で、牧野さんが理想とする保育実践がはじまりました。アタッチメントの学びを取り入れた結果は、ほどなく現れます。
絵本の時間になると、ふらっとその場から離れちゃう子がいました。絵本に誘うと嫌がって泣いてしまい、逃げてしまいます。
園に通うようになって4か月後、絵本の時間になると、自分から座って待っていてくれるようになり、本人のワクワクが伝わってきます。絵本も最後まで一緒に楽しんでくれるようになるだけでなく、おやすみなさいで自分からお昼寝用のお布団に入ってくれるようになりました。
ほかにも、公園の小さな丘を怖がって一人で登ることができなかった1歳の園児は、四つん這いで登れるようになり、立ってのぼれるようになり、おしりをついて降りられるようになり、転びながらも歩きながら降りられ、小走りでも降りられるようになりました。
発達支援の場面では、おうむ返しの発語だった子が自発的な発語をするようになったり、2単語のみの発語だった子がオウム返しの言葉で色々覚え、自分から状況に応じた単語を伝えてくれるようになるケースもあります。
保護者からも「子どもが出来る事が増えた」とのうれしい言葉をもらえているそうです。
とはいえ保育園経営は、まったく平たんではありません
「働く人目線の職場」を目指して立ち上げた「葉っぱの家保育園」ですので、職員が休みを取りやすい態勢をつくるため、牧野さんのほかに2人の保育士を採用しました。さらに、牧野さんと同じ目線で「よりよい保育」を実現するために、この二人の保育士には、園が費用を負担して協会の講座を受講してもらいました。
しかし、採用したうちの1人は、講座の初日に連絡が取れなくなり、そのまま音信不通になってしまいます。すぐに、新しい人を募集し、なんとか予定通りの態勢を構築してスタートしたそうです。
しかし、保育園経営は甘くありません。保育はプロでも、経営は素人の牧野さんに、園児集客の壁が立ちはだかります。経営でもっとも重要なマーケティングの問題です。さらに、利用者が集まらない状況に、ひとりの職員から「保育がしたくて入ったのに」と不満が噴出し、早々に退職されてしまいます。以前の同僚に声をかけ、パートで入ってもらってしのぎます。しかしこんどは、たった一人残った正規職員が、心身不調で療養休暇、そのまま退職となってしまいます。ここでも、かつて働いていた園の保育園看護師の同僚が助けに入ってくれて、何とか態勢を整え直すことが出来ました。これはマネジメントの問題です。
失敗から学ぶことで、経営力は強化されます。その後マーケティング施策として取り入れた「使いたい放題」が功を奏し、集客は安定して、元の同僚2人との保育現場も、うまく回るようになります。
つぎつぎに降りかかる保育園経営の問題は、ついに・・・

そんな中、今度は設備の問題が降りかかります。これが「葉っぱの家保育園」の存続そのものを脅かす事態になります。
保育園は、消防法で一般事務所や店舗より厳しい規制が課されます。消防署の立ち入り検査で、園が入る建物の全テナントの火災報知器が連動する大掛かりなシステムを導入する必要があることが分かったのです。建物のオーナーは、そこまでの設備負担は出来ないという回答です。
「葉っぱの家保育園」が園を継続するためには、①連動型火災報知器を自費で負担するか、②然るべき物件に移転するか、の2択を迫られる事態になりました。
いま、牧野さんは、クラウドファンディングを立ち上げて、支援を求めているそうです。「小さな保育園存続の挑戦」で検索すると、キャンプファイヤー(クラウドファンディング)のページがみつかります。また、園の見学なども応じてくれるそうなので、もし興味のある方は、「葉っぱの家保育園」へ直接コンタクトしてみてください。
廣島から牧野さんへひとこと
牧野さんは、もともと当協会の講座を受講されたときは、公立園で保育士として勤務されていました。「保育をよくしたい」という強い信念を持った勉強熱心な保育士さんで、全国大会にも積極的に参加してくれて、その後、私立園に移られてからも、質問や悩みをお聞きしていたので、わたしにとっても、当初から印象深い方でした。
つい数年前の全国大会でお会いした時に、「保育園を立ち上げて、いま園長をしています!」と聞いて、驚いたことを覚えています。既存の園の園長になるケースや、経営者が保育園経営に乗り出して園を立ち上げるケースは、たくさん見てきましたが、保育士さんみずからが、園を立ち上げるケースは、わたしが知る限りレアケースと言えます。そんなこともあり、わたしも密かに牧野さんの園を見守っていました。
牧野さんの発表をお聞きして、マーケティンやマネジメントなどの経営上の問題はありましたし、火災報知器の件を含め、資金調達の問題もありました。しかし、それをひっくるめても、わたしは安心しています。なぜなら発表をとおして、牧野さんに、保育においても、経営においても解像度の高い「志し」が見えたからです。人は、「志し」に集まってくれます。園児や親御さんもそうです。職員もそうです。志しがあれば、マーケティングもマネジメントも、資金調達も最終的にうまくいくでしょう。

おまけ:存続の危機に関して
最後に、わたしから、存続危機の原因となっている火災報知器の問題についてひとこと。くわしい条件がわからないので、断定はできませんが、今回のケースでは、移転よりも連動型火災報知器を設置する方向で可能性を探ってみる方が、現実的だと思います。まずは、導入費用の見積もりを取ってみてください。買取、リースのほかに、警備会社をとおして導入することも考えられます。最低限、消防法をクリアするためには、どれだけの設備が必要かを、具体的に金額で把握することが目的です。契約する必要はありません。
その上で、オーナーさんとの交渉において、ゼロか百かではなく、一部負担を持ちかけてみてください。導入メリットは、オーナーにもあるからです。設備がアップグレードされるだけでなく、これからテナントを付けるときに、より広く募集できるメリットも生まれます。今後のテナント募集において家賃アップも可能となります。
また、オーナーに設備を導入してもらう代わりに、その導入費用を、家賃の上乗せで園が負担する交渉も可能です。家賃で分割払いするイメージです。設備自体は、オーナーのものですので、その導入費用を家賃に上乗せしてもらうのです。それならば、新たな借り入れをすることなく、月々の固定費で賄うことが出来ます。その際、いくらの上乗せが妥当かを判断する際に、最初の見積もりが参考になります。 牧野さんの園は、志しをもったすばらしい園です。ぜひ存続にむけて、ひと踏ん張りしてください。これを乗り越えた牧野さんは、経営者としても一皮むけていると思います。貴重な発表を、ありがとうございました。

目次
- 開会のあいさつ
- 1日目:全国大会スキルアップ講座
- 『キッズマッサージ/アタッチメント・ジム 全面リニューアル』
- 2日目:育児セラピスト全国大会シンポジウム
- 東京家政大学 子ども支援学部 教授 / 特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 副理事長
保坂 遊 先生 - 基調講演「アートと非認知能力の育ち」
- ▼ 優秀実践者発表
- 「志し」をカタチにして、保育園を立ち上げた保育士の物語
- ― 保育 部門 牧野 クルミさん
- 実家の「庭」からはじまった子育て支援の輪
- ― ダイバーシティ部門 衣川 由理さん
- ランチミーティング
- 恒例!お悩みスーパーバイズ2025