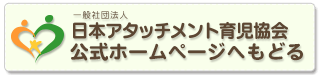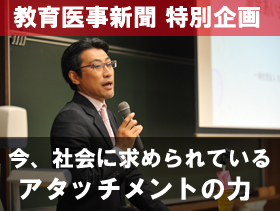非認知能力への体からの アタッチメントアプローチ

今年2025年の全国大会で、スキルアップ講座としてリリースした、全面リニューアル版キッズマッサージ/アタッチメント・ジムは、もともと2010年の第1回全国大会でリリースした最初のスキルアップ講座でした。
15年前(2010年)は、非認知能力という言葉もコンセプトも、まだありませんでした。J・ヘックマンが非認知能力を提唱した“Giving Kids a Fair Chance”が出版されたのは2013年、そしてわたしが、はじめて講座で非認知能力を紹介した「あそび発達インストラクター講座」は、2016年、さらにその後、非認知能力が一般に知られるようになり、その重要性が注目されるようになったのは、コロナ禍の2020年に入ってからのことです。
ところで、この非認知能力を育てるカギとなるのは、幼少期における「体からのアタッチメント・アプローチ」です。「キッズマッサージ/アタッチメント・ジム」が、まさにこのコンセプトにピッタリ当てはまるメソッドだったことは、当初からわたしも承知していました。そこで、今回のリニューアルで「キッズマッサージ/アタッチメント・ジム」を、非認知能力の文脈で再構築することにしました。
実際に、リニューアルした講座を披露し、受講生のみなさんの反応を受けてみて、想像していた以上の手ごたえを感じています。
体へのインプットによる“Impress”(感情・感動)を起点とするキッズマッサージは、情緒の育ちに働きかけ、非認知能力を育てます。
体からのアウトプットによる“Express”(動きの出力)を起点とするアタッチメント・ジムは、運動の育ちに働きかけ、非認知能力を育てます。
この情緒と運動をそれぞれテーマに持つ二つのメソッドは、非認知能力という着地点によって、ひとつに繋がり、相互に循環する“らせん成長”を実現します。
情緒 + 運動 → 非認知能力 → おまけとしての認知能力
これまでの教育において圧倒的な価値基準であった認知能力が、いまや非認知能力に完全に置き換わったことを、教育者として本当の意味で理解する、発達のメカニズムとして理解する、概念の根っこまで解釈する。そういうものに仕上がったという手ごたえを感じています。

非認知能力って、けっきょく何なの?
最初に、非認知能力についての全体像をお伝えしました。
●0・1・2歳の土台形成期
●3~6歳の能力開発期
●7~9歳の活用・修正期
非認知能力とひとくちに言おうと試みても、それほど単純なものでないのは、他の発達理論と同じです。
非認知能力というと、能力開発に目が行ってしまいがちですが、むしろ大事なのは、その前の土台形成であることは、みなさんの想像通りです。そして、そのあとの活用・修正の段階も見過ごせません。
この全体像のすべてを捉えたときに、はじめて非認知能力の獲得が実現します。一つにフォーカスしても機能しません。飛び級して抜かしても機能しません。ひとつでも足りなければ、機能しません。階段を一段ずつ昇ることで、3つの成長期を、連続的に体験した先に、非認知能力の獲得が実現されます。
AKMアタッチメント・キッズマッサージ
はじまりは、情緒系のインプット非認知能力
キッズマッサージが担う情緒系の発達は、体へのインプットによる“Impress”(感情・感動)によって形成され、非認知能力の土台形成において重要な役割を果たします。マッサージをとおして、「気持ちイイ」「うれしい」「お母さん大好き」といった感情や感動が湧き出ることによって発達します。
この土台形成がしっかりと厚く成されていないと、その上に乗っかる能力のボリュームは限られてしまいます。
最初に獲得する非認知能力における中核要素は、「①自己肯定感」です。これがなければ、何も始まりません。すべての能力の土台です。この自己肯定感が獲得できていなければ、その子が何歳であっても、キッズマッサージの最初の段階から始める必要があります。
自己肯定感を獲得すると、「もっと認められたい!」という意欲がめばえます。お母さんや保育士との関係によって意欲がめばえると、もっと広い世界へと視野が広がり、興味関心が広がります。そして「好奇心・探求心」を獲得します。
ここまでが、情緒系の非認知能力のメインテーマです。「自己肯定感」「好奇心・探求心」というたった2つの要素ですが、非認知能力の育ちにとって、必要不可欠であり、これを豊かに育てれば、それだけ高い非認知能力の育ちが期待できます。
ここからは、キッズマッサージは、アタッチメント・ジムのサポート的役割、あるいは補完・強化する役割を担います。
AGMアタッチメント・ジム
動き・行動によって育つ運動系のアウトプット非認知能力
アタッチメント・ジムが担う運動系の発達は、体からのアウトプットによる“Express”(動きの出力)によって形成され、非認知能力における能力形成を担います。「やってみる」「感じる(内省する)」「別のやり方でやってみる」という行動によって、「できた!」という成功体験を最終的に得る体験をすることで育ちます。
非認知能力の最初の中核要素である「自己肯定感」「好奇心・探求心」において、アタッチメント・ジムは、キッズマッサージのサポート的役割、あるいは補完・強化する役割を担います。
「①自己肯定感」「好奇心・探求心」が原動力となって、子どもは行動を起こします。行動の結果、うまくいくこともあれば、そうでないこともあります。ほめられることもあれば、そうでないこともあります。その結果を、子どもは内省して、つぎには違うアプローチを試します。
この段階は、子どもひとりの中で完結することはありません。必ず親や先生が、いっしょに、あるいはとなりでサポートすることが不可欠です。「もう一回やってみよう」「こうしたらうまくいくかもよ」この過程で、子どものなかに「自律心」や「自制心」がめばえます。アタッチメント・ジムには、こんな教えがあります。「まずは、体をコントロールできるようになる。すると心もコントロールできるようになる」
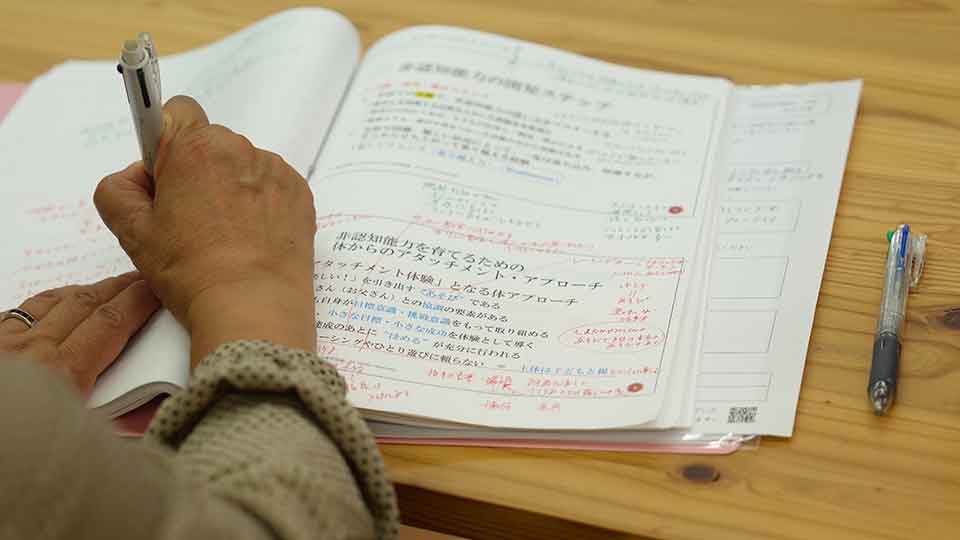
最終的に子どもは「できた!」という成功体験を得ます。こうした「小さな成功体験」の積み重ねが、非認知能力においてもっとも中核的な要素の2つ目である「②やり抜く力(GRIT)」を獲得します。
一方で、「自己肯定感」が満たされ、心のコントロールができるようになると、子どもは他者に目を向けられるようになり、「他者性」が出てきます。お母さんの動きに合わせて動く。おともだちの気持ちを想像する。こうして、「社会性」を身につけます。「他者性」と「社会性」を身につけると、非認知能力における中核要素の3つ目、いっしょに行動を共にする「③協調力」が獲得されます。
「②やり抜く力(GRIT)」によって、子どもは“やっていること”に没入することが出来るようになります。それによって4番目の中核要素「④集中力」を獲得します。
一方で、「③協調力」は、言語能力の高度化とともに、「⑤コミュニケーション力」の獲得へとつながり、非認知能力は完成へと向かいます。

二つをもって非認知能力を育てるメソッドとして機能する
アタッチメント・ジムは、体の動きのアウトプットによる運動メソッドですが、そのプロセスにおいては、キッズマッサージの体へのインプットによる情緒に働きかけるメソッドが、同時に機能しています。
非認知能力育ちにおいて、最初にキッズマッサージがメインの役割を担います。その時期にアタッチメント・ジムは、キッズマッサージを補完し、強化します。その後、「②やり抜く力(GRIT)」の獲得以降は、アタッチメント・ジムがメインの役割を担います。その間、キッズマッサージは、アタッチメント・ジムを補完・強化するだけでなく、子どもの経験・体験に対して内省を促す気づきや発見を与えることで、非認知能力の育ちをあと押しします。
情緒系も運動系も、非認知能力の育ちは、すべて体験から
最後に、「体験」についてお伝えしました。キッズマッサージによる情緒系の非認知能力も、アタッチメント・ジムによる運動系の非認知能力も、子どもにとっては、すべてが「体験」のなかで起きていることです。
つまり「どんな体験をしてきたのか」に尽きるわけです。非認知能力の育ちは、然るべき時期に、然るべき体験をすることです。しかし同時に「決まった“ある体験”をすればよい」と言うことではないのが難しいところです。
そのことを、ドイツ語の“Erlebnis”(エアレープニス)という一般的な体験とは一線を画す「真の体験」を意味する言葉を紹介して説明しました。
体験は、見た目には同じ行動をしていても、子どもそれぞれのなかで、違う物語が動いていて、ひとりひとり違うことが起こっています。そういう体験こそが「真の体験」であり、非認知能力を育てる体験となり得るということです。
「非認知能力の成長サイクル」を提供するメソッドの完成
今回のスキルアップでは、新規、再受講ともに、「キッズマッサージ/アタッチメント・ジム」の両方を、受講者全員に学んでいただきました。そうして確信したことは、どちらか一方で終わってしまっては、本当にもったいないということです。
メソッドとしては、それぞれ一方だけでも成立します。しかし、非認知能力の育ちの観点で言うと、2つを修得することで「非認知能力の成長サイクル」を提供できるメソッドとして完成するものだからです。そのことを明確に認識しました。
もう一つ発見したことがあります。非認知能力とアタッチメントは、同じ線上に存在するものであることは、数年前からお伝えしているとおりです。だからこそ、今回の「キッズマッサージ/アタッチメント・ジム」は、アタッチメント理解の次元が一段上がるものに仕上がったと実感しています。
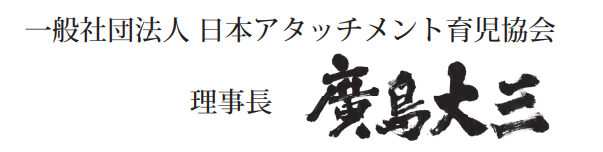
目次
- 開会のあいさつ
- 1日目:全国大会スキルアップ講座
- 『キッズマッサージ/アタッチメント・ジム 全面リニューアル』
- 2日目:育児セラピスト全国大会シンポジウム
- 東京家政大学 子ども支援学部 教授 / 特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 副理事長
保坂 遊 先生 - 基調講演「アートと非認知能力の育ち」
- ▼ 優秀実践者発表
- 「志し」をカタチにして、保育園を立ち上げた保育士の物語
- ― 保育 部門 牧野 クルミさん
- 実家の「庭」からはじまった子育て支援の輪
- ― ダイバーシティ部門 衣川 由理さん
- ランチミーティング
- 恒例!お悩みスーパーバイズ2025