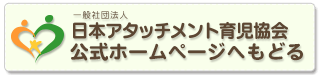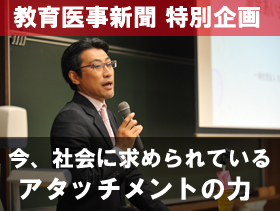第16回 育児セラピスト全国大会in2025 保坂遊先生 基調講演「アートと非認知能力の育ち」

アートと非認知能力の育ち
東京家政大学子ども支援学部 教授
特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 副理事長
保坂 遊 先生
保坂先生は、東京家政大学の保育士養成で教鞭をとられるだけでなく、彫刻家として作家活動もされており、「アートと人の関わり」を研究テーマに、アートがどのように社会の中で機能し得るのかを追求しておられます。そんな保坂先生は、「アートは、生活のなかに根差したものであり、特に『子どもとアート』の関わりは、われわれが思っている以上に深いのだ」とおっしゃいます。
保坂先生の現在をたどると、もともと美術大学の学生だったころ、先輩の誘いで保育園の絵の先生のバイトをしたころに遡ります。美大生としてのアート活動が苦しくなっていた当時、子どもたちの自由な発想、あふれ出るエネルギーに元気をもらい、大いに刺激をもらったそうです。「アートを通じて子どもたちと関わることを一生の仕事にしたい」というイメージを持つようになったのはこの頃からでした。
大学の保育者養成で教えるようになった今も、子どもたちと直接かかわる時間は欠かせないという考えから、月に一回は現在も、臨床美術士として、保育園の子どもたちと、アートを通じた関りを持つようにしています。
アートによって、自尊心と自己肯定感を取り戻す
臨床美術は、もともとは「認知症」のケアとしてのアートの可能性を形にしたものだったそうです。認知機能不全に対して、非認知的アプローチ、つまり感覚脳を刺激することが効果があることがわかり、造形やアート全般を、これに取り入れようというものです。
認知症というのは、“できていたことができなくなる”ことが、その特徴です。そこには、自尊心や自己肯定感情が失われていくという現実があります。臨床美術は、認知症の進行を抑えることが期待されるだけでなく、この自尊感情に大きく働きかけることができるアプローチであると保坂先生は言います。それは、アートというのは本来、自己表現であり、人それぞれのものなので、褒めたり、尊重したりする機会をつくれるアクティビティであることが大きく関係しています。
「アートによって褒められることで、人は穏やかになる。それは、本人だけでなく、家族や介護する方にとっても相乗効果的によい影響をもたらす」
保坂先生はそうおっしゃいます。
アートは、子どもたちにも癒しと成長をもたらしてくれた
臨床美術が必要とされたのは、老人だけではありませんでした。児童養護施設の子どもたちは、その50~60%以上の子どもが、虐待を経験しているのが現状です。こうした子どもたちには、何かしらのトラウマ(心的外傷)を負っています。
アートによる自尊心と自己肯定感へのアプローチは、この子たちのトラウマの解消にも効果を発揮しています。
子どもは、生まれながらにして表現者である
保坂先生は、7~8か月くらいから、赤ちゃんにクレヨンを持たせてみるそうです。1歳にもなれば、クレヨンで紙に色が付いたことを“たのしい”と感じて、絵を描くようになります。「それは、まさに表現者としてのDNAがあることの証だ」と言います。同時に、音楽がかかれば、リズムに合わせて体は動いたりもします。これもアートです。
このような自分がアクションを起こす能動的な「感性」は、人間だけのものだと思います。これこそが、アートにおける「表現者としての才能」と呼ぶべきものだと思います。
「その意味で、才能のない人は、この世にいないとわたしは思うのです」
歌いたい、踊りたい、描きたい・・・こうした「表現したい」という衝動からアートすることができるのは、人間だけに備わった才能です。この才能を、どう子どもたちに育てていくかが、わたしたち大人に課せられた命題だと考えています。
子どもの発達と表現
子どもの発達は、「こころ」・「からだ」・「あたま」の3つから成っていると、保育士を目指す学生たちに教えています。
「こころ」は、まさにアタッチメントの根幹をなすところの情緒や社会性です。喜怒哀楽といった感情や感動といったものが育ち、やがて自我のめばえを経て、興味や関心が育ちます。
こうして、感性が育ってきます。日本語で言う “感性”は、英語には当てはまる単語がありません。 “impression” + “expression”という2つの概念としてはじめて捉えることができるものです。感性とは「インプットして感じたものを、アウトプットして外へ押し出す」この一連の機能を差しています。これは、保育所保育指針にも掲げられていることでもあります。
ここで最初に大事なのは、「感じること」です。感じると、それを伝えたくなって「表現する」。保育で大事なのは、「お絵描きしましょう」と言う前に、何かを「感じる」インプットが十分になされる必要があるのです。これをとおして、褒められ、承認されることで意欲が高まり、それが主体性や想像力となります。その先に、共感や社会性が育まれ、「こころ」は育ってゆきます。

「からだ」は、運動機能や感覚の育ちです。体が大きくなるのに伴って、身体機能が高機能化してゆきます。
アートに関して言えば、拇指対向性といって、親指の動きが精緻になり、他の指と向き合って動かすことが出来るようになります。これは、人間の一番の進化であるとも言われています。これによって、「つかむ」という動きが高度化されます。そうして、クレヨンをもったり、ハサミが使えたりするようになります。さらに「協応」といって、目で見たものを、それに合わせてつかむようになり、アートによる表現は豊かさを増します。
「あたま」は、知的発達の部分で、認知や言語機能の育ちを担います。関心、好奇心によって探索や試行をすることにより、さまざまな体験をして、概念形成がなされます。これは、言語発達によって、さらに深みを増してゆきます。
アートにおいても、この概念形成によって、表現に創意工夫や試行錯誤による豊かさが生まれ、より高度な表現につながってゆきます。
発達段階と描画の関係
ここでは、ピアジェの認知発達論に対応して、子どもの描画(絵を描く表現)が、どのように発達していくのかを解説していきます。
0~2歳:感覚運動的段階

なぐり描き期:頭で考える(認知)よりも、まず感じたことで活動して、それが楽しいと感じられる段階です。
スクリブルと言って、意味のない絵を描くことから始まります。手を動かすこと、色が塗られること、それらが相まって楽しいから描いた絵です。2歳くらいまで、こうした絵を描くことで、指と手、肘、肩を連動して動かすようになります。専門的に観ると、このスクリブルは、何歳何か月の子のものだ、と言うことがわかったりもします。
スクリブルは、終わりがありません。グルグルと描き続けます。やがて、丸が描けるようになります。われわれは、これを「丸が閉じる」と言います。丸が描けたとき、子ども本人も「ハッ!」と驚いて指差しをします。この時、「丸」と言う概念を、子どもは獲得するのでしょう。これを何度も見てきました。大好きな感動の瞬間です。
2~3歳:表象的思考段階

象徴期(シンボル期):丸が描けるようになると、この「丸」の中に、子どもは何かを想像して絵を描くようになります。お母さんだったり、アンパンマンやクマさんかもしれません。そうして丸は、シンボル(象徴)になってゆきます。こうして、表現に方向性が生まれ、豊かさを増してゆきます。
3~4歳:象徴的思考段階

前・図式期(カタログ期):シンボルを描く方向性が生まれてくると、丸がリンゴになったり、たくさんの丸がブドウになったり、三角のイチゴが描けるようになったりします。これらを、紙のいたるところに描くようになります。これをカタログ期と言います。自分の知っているもの、描きたいものを、カタログのように全部一枚の紙に描きます。
4~7歳:直観的思考段階

図式期(GLの発生):こうして、いろんなカタチが表現ができるようになると、いよいよ幼児が描く絵になってきます。太陽、空、雲、女の子、チューリップ、ひまわりといったように、一つ一つの概念がしっかりと描かれるようになります。
この時期に来ると、カタログ期の絵と違って、上を空、下を地面と決めて、構図をとるようになります。この「天地」というのは、大きな概念で、グランドライン(GL)と言ったりします。天に空や雲、太陽が描かれ、地にチューリップやひまわり、女の子が描かれるようになり、本格的な概念が形成されるようになります。
アートは感性?概念?

概念を描くことがアートなのかというと、そうではありません。アートの世界には、写実的な絵もあれば、抽象画のような絵もあります。
うえの絵は、3人のお姫様やお花、舞台や装飾が描かれています。この絵は、概念を描いています。われわれ大人は、子どもが、こうした絵が描けるようになると「絵が描けるようになった」と安心したりします。逆に、グルグル描きのような抽象的な絵ばかりをずっと描いていると、発達を心配したりします。
概念を描いた絵は、知性の表現、抽象的な絵は、感性の表現と言えます。どちらの表現も、アートとして価値があるのですが、われわれは、もっと感性の表現や言葉に出来ない、形に出来ないノンバーバルな表現の可能性や才能に目を向ける必要があるのではないでしょうか。
本来は、知性の表現も、感性の表現も、両方大事にされるべきものです。この視点こそが、今回お題としていただいた「アートによる非認知の育ち」につながっていくのではないかと考えます。
注目される非認知能力の重要性

認知能力というのは、IQ(知能指数)のように、数字で測れる能力で、これまで学校教育で重視され、子どもの学力の象徴として機能してきました。具体的には、記憶力・言語力・計算力などを指します。
これに対して非認知能力は、文部科学省が「生きる力の基礎」として掲げる気質や性格的な特徴です。この非認知能力は、J・ヘックマンが提唱した経済学的視点におけるものだけでなく、OECDが掲げる“汎用的スキル”や“社会情動的スキル”など、さまざまに派生してその特徴が述べられているので、ここで述べるのは、その中のほんの一部と理解してください。
非認知能力に関して、もっとも重要なのは「自分を理解する」という要素だと考えます。自己認知・自己理解・自己肯定感といったもの、それらが原動力となって意欲やモチベーションがどう発現するのか、さらにそれらをやり続ける継続力、自己コントロール(自制心)、失敗しても立ち直って前に進むレジリエンスをいかに発揮するかといった能力です。それらをとおして、社会適応性や創造性を獲得してゆきます。
非認知能力と幸福感
これまで認知能力は、高い学歴やよい就職を約束し、経済的な成功をもたらす需要な要素でした。しかし、ヘックマンが経済学の観点から解明したのは、「こうした認知能力による経済的な成功は、人生の幸福度を約束するものではなかった」ということです。
人の幸せは、稼いだお金の額とは相関しません。幸せを感じる要素として重要なのは、むしろ非認知能力の方でした。
自尊心や自己効力感が高い人ほど幸福度が高い。共感性や協調性が高い人は、人間関係の満足度や社会的つながりが強い。レジリエンスが幸福度を左右する。さらにOECDの調査では、「社会情動的スキル(非認知能力)を持つ子どもは、学業成績がよいだけでなく、将来の幸福度や健康にプラスである」と結論づけています。
つまり、「幸せに生きる」という視点に立つと、非認知能力が重要であると言えそうです。
表現は「自己理解」のためのプロセス!

この非認知能力とアートはどう関連してくるのかを考えてみましょう。非認知能力において、もっとも重要なのは「自己理解」であると、先ほど述べました。アートによる表現は、まさにこの自己理解のいとなみと言えます。
アートでは「表現は『自分自身を創る』営為(ワーク)である」と言ったりします。なにか思っていること、感じていることは、意外とぼんやりしていてつかみどころがありません。それを表現してみて、はじめてその輪郭が見えてきて「こういうことだったのか!」と発見することがあると思います。
絵を描くという行為は、描きたいものが明確に頭の中にイメージされていて、それを描き出すことのように考えられがちですが、実は何かわからずに描いていて、出来上がっていて「自分が描きたかったのは是だったのか」とわかる、ということがよく起こります。
作品は、自分の思考や感情、感性を塗り重ねた記録です。その作品が、うまいとかキレイだということとは別に、作者が、どんな思いや感情を積み重ねてきたのか、という視点で作品を観るようにしています。特に子どもには、この視点がとても重要です。
子どもにとって、絵を描くことは、文章表現であり、日記のようなものだと考えられています。
わたしたち大人は、そのいとなみにおけるガイド役に過ぎません。あくまで、すべての決定権は子どもに委ねられていて、子どもが紡ぎだす「自分なりの表現=自己表現」をともに楽しむ姿勢が重要です。こうした記録を積み重ねることで、子どもの自己理解が進みます。それは、非認知能力の育ちと言い換えることができるのだと考えます。
意欲と主体性を育む

では、非認知能力の中核的要素である「意欲と主体性」について考えていきましょう。意欲は、どうやったら育つでしょうか?「やりなさい」と強制や命令されたら育ちません。「おもしろそうだな!」という好奇心が意欲の源泉です。子どもが自分でそれを見つけることもあれば、大人が「これどう?」と提示することもあります。それを子どもが「おもしろそう」と感じるのは、素材や色、形であったりします。
「おもしろそう」の意欲は、「やりたい」につながりモチベーションを生みます。そして、「描いてみる」という実践にうつるでしょう。このプロセスでは、子どもがうまく出来ないことが起こります。たとえば、折り紙を折っていて、うまく折れないなどです。ここで、あきらめてしまうと、つぎの非認知能力の育ちにつながりません。もう一回チャレンジすることを応援したり、うまくいくように導いたりする大人の援助は重要です。そうすると「もっと描く」「もう一回やる」といって集中や継続が身につきます。
その先には「できた!」という達成感、そして「またやりたい」という期待が生まれ、小さな成功体験を積むことが出来ます。
この「主体的な能動性を継続させるサイクル」を、子ども自身が自分で回せればいいのですが、その過程では、提案をしたり、壁を乗り越える手伝いをするわたしたち大人の手が、必ず必要となります。
リフレーミングが新しい発想を生む



リフレーミングという言葉をご存じでしょうか?
フレームというのは、固定概念です。わたしたちがあたりまえにそう思っているモノの見え方・あり方です。そのフレームを捉えなおして再構築するのがリフレーミングです。
美術では、間近でとらえていた作品を、遠くから眺めてみると、違った見え方をして発見があることがよくあります。絵を描くときは主観です。それを離れてみた時に客観的な視点が加わります。それを踏まえてまた主観で描く。この主観と客観をひたすら行ったり来たり(往還)するのが美術と言えます。
こうして行為のプロセスが作品に記録され、蓄積されていくのは、美術の特徴かもしれません。音楽というのは、その時の歌や演奏はその瞬間のもので、形としては残りません。そこが音楽の魅力とも言えます。一方で美術は痕跡です。一つ一つの痕跡をリフレームしながら、つぎの痕跡を塗っていく。美術家は、リフレームのために、ときには作品をひっくり返してみたりもします。
このリフレーミングが、新たな発想を生み、ときにはイノベーション(革新)さえももたらします。
レジリエンスを育むやわらかあたま!
つぎに、非認知能力の中核要素としての「レジリエンス」の話をしたいと思います。
なにかをやり続けるときや、目標達成を目指すときに、わたしたちは、よく根性論を持ち出します。こうした「がんばる」という精神論は、アートにおける表現の世界では、あまり馴染みません。
アートにおいて、やり続けるために大事なのは、ものごとを柔軟に考えられる“やわらかあたま”です。さきほどお話ししたリフレーミングによって、「もっとこんなことしたらおもしろいな」という発想の転換のようなことの方が、やり続ける原動力になります。
困難な状況でも、見方・考え方・捉え方を変えて、しなやかに対応してみたら、おもしろさが見つかる、解決策が見いだせる、そうした“やわらかあたま”で対応した経験の積み重ねが、非認知能力において重要なレジリエンスを育みます。
感じる心の開放

表現活動は、五感の働きが非常に重要です。そのためには、リラックスした環境に身を置く必要があります。とくに子どもの世界では、楽しい、おもしろい、という感情や、なにをやっても大丈夫という安全、安心が保障されていないと、感覚が自由に働きません。
その意味で、子どもたちとアート表現をやるときは、最初の言葉かけを大事にしています。今日は、いかに楽しいこと、おもしろいことをやるのかという期待感を演出して、子どもたちの感じる心を開放することに多くのエネルギーを使います。これがうまくいけば、子どもたちのクリエイティビティは全開になります。
この「あらたな価値を生み出す力=クリエイティビティ」は、子どもに最初から備わっている力ではなく、総合的な能力獲得とともに育っていくものであると考えます。感じて、考えて、表現してみて、そうした蓄積によって育つものです。幼少期の活動が、このクリエイティビティを左右すると考えます。
みんなで描く、みんなで造る

つぎの非認知能力の要素として、「社会性」の話しをしましょう。
アートは、個人の活動だけでなく、他者と共同で行うこともできます。子どもは、ひとりひとりが違うことを考えています。他の子どもといっしょに、ひとつの同じ作品に取り組んでいるときに、となりの子を見て、自分とは違う感性を発見します。そこには刺激や、新たな発想が生まれます。
また、共同で作品を作ると、ひとりでやる時よりも大きな作品が作れます。ひとりの力では出来ないことも、みんなでやればできるという経験をすることができます。その過程では、ほかの子の表現を認め合ったり、共感したり、協力する場面をとおして、社会性が育まれます。これを可能にするのが、アートの大きな利点です。
自分に自信を持ち、認め合う心を培う

いよいよ非認知能力におけるもっとも基本的で、もっとも重要な要素である「自己肯定感・自尊感情」のお話をします。
「アートに正解はない」とよく言われますが、むしろ「すべてが正解である」と言っても良いと思っています。とくに幼少期は、全員正解でいいんです!「自分なりの表現を豊かにする」ことこそが大事なのです。
そうすると、わたしたち大人は、とにかく認めればいいんです。アドバイスも評価も必要ありません。むしろしてはいけません。子どもにとって大事なのは、「自分の表現が認められる」ことです。これが、自己肯定感や自尊感情につながってゆきます。
「じぶんが表現することは、すべて認められるんだ!」ということを、大人は保障する必要があります。そうして、自分が充分に認められて、子どもは、はじめて他者の表現にも目を向けることが出来ます。0~3歳くらいまでは、シャワーのように、ほめことばで子どもたちを認めていきます。そうして4~5歳になってくると、ほかの子の作品をほめ始めます。これは、教育として重要なことだと考えています。
表現の自由が保障される安心・安全の場

保育におけるアート活動を考えた時、作品を作るだけで終わっては、もったいないです。ぜひ “認める場”をつくってください。そこでおススメするのが「鑑賞会」です。
子どもたちの絵を貼って、みんな集まって、ひとりひとりに向けて、先生が“ほめ言葉のシャワー”で認めます。このとき、ネガティブな言葉や評価は一切必要ありません。
そうすると、子どもは作品を描いたら、いつも先生がほめてくれるということを実感し、安心・安全の場として機能するようになります。すると、他者に目が行くようになり、おともだちに興味を持ち、ほめたりすることが出来るようになります。
保育園の日常生活の中では、いつも認められるような場面ばかりではありません。だからこそ、絶対的に安心・安全の場として機能する居場所として、アートを活用していただきたいのです。「表現の場」だけは、絶対にほめてもらえる、というルールとして運用してもらえばよいと思います。
アートで個性を承認するための大人の注意事項
ここまでで、アート活動によって、子どもの非認知能力や成長・発達を促すことができることがお分かりいただけたかと思います。ここでは、そのための大人の側の注意事項をまとめようと思います。
大事なことは、固定概念や大人の価値観を持ち込まないで、つねにリフレーミングして対応することです。
形が変わっていることは、間違いではなく、オリジナリティです。大人が思った色と違った色を選ぶのは、個性的であるがゆえです。はみ出して描くのは情熱的である証です。終わらないでずっと描いているのは、表現に対するこだわりが強く、集中力があるからです。始められないのは、本人が納得していないからです。
臨床美術の紹介
臨床美術は、脳活性化を促す独自のアートプログラムによる創作活動によるアートセラピーです。心理学をベースとして、作品の心理的背景を読み取るサイコセラピーとは違い、創作活動、表現活動そのものに効果があるというアプローチです。創始者の金子健二先生が、芸術家の視点から立ち上げ、体系化したもので、知性に基づく概念ではなく、感性で自由に表現することによって、脳活性や癒しを得ることが特徴です。
もともとのはじまりは、東京藝大を出て、彫刻家として第一線で活躍していた金子先生が「アートを社会的なものにする」というテーマを掲げて、子どもの美術教育に乗り出し「小さな芸術家のアトリエ」を開講したところに原点があります。
臨床美術のアプローチ
1.感性の刺激:「感じる」ことから始まります。五感を刺激して、モチベーションを高めます。
2.美術制作活動:描く・作るといった表現活動をとおして、個性や創造性を引き出します。
3.鑑賞会:作品を展示し、先生に褒めて認められる安心・安全の場をもち、自己肯定感と他者理解を育みます。
まとめ:存在はそれぞれのカタチ
そもそも、わたしたちは、特性、環境、育ち、関心、趣向・・・ひとりひとりが違う存在です。それを自他ともに認められた時に、アイデンティティとして形成されます。

ところが、子育てや保育の世界では、子どもを発達として捉え、平均や均質を志向してしまう傾向があります。「この年齢なら、これができる頃だよね」と平均値でとらえてしまいます。発達曲線は、平均から導き出した指標に過ぎません。大人になれば、それぞれ違う形を形成してゆきます。
発達段階として大事である反面、「ひとりの子どもがどのように育っていくのか」を個別にみた時、個性を認める・唯一解のないアートと保育・子育ては、非常に親和性があると思っています。この親和性を、これから、もっと現実化して活かしていきたいと考えています。
ワークで臨床美術を体験しました



保坂先生のお話しを聞いて、廣島の所感
保坂先生がおっしゃるように、大人は、それぞれの違いが認められて、みんなが違う形をしているのに、子どもの発達は、どうしても平均でとらえられてしまいがちです。そこには、安心したい親の本音があるのだと思います。平均にはまっていれば安心。となりの子と同じなら安心。点数が良ければ安心。

今回、非認知能力をテーマに、アートの観点から保坂先生にお話しいただいたのは、こうした親が子どもに一方的に抱く安心の根拠をひっくり返す目的がありました。
本来、子どもの育ちは、百人百色でなければなりません。それを保障してはじめて、非認知能力は育ち、発達が進みます。これは、100年以上前に、フロイトが、モンテッソーリやピアジェが言っていた古典そのものです。しかし実際には、そのように子育てや保育を実践するのは、現実的でないところが確かにあります。
一方で、アートにおける表現は、いつでも自由が約束されています。誰もがアートとは、そういうものだと納得しています。図工の授業で、ピンクの犬を描けば、写実性がないと低い評価を受けるかもしれませんが、アートの世界では、それは個性的であり、興味深い作品として称賛されるかもしれません。保育の現場では問題行動である多動だって、アートの世界ではエネルギッシュで創造的に働くかもしれません。
大人の固定概念や平均で評価されてしまいがちな子どもの世界に、アートという自由さを認められる場、他と違っていることを個性と認められる場、いつでもほめてもらえる場を作ることは、現代の子育て・保育にとって、ひとつの希望の光なのかもしれません。それによって、開花する非認知能力、守り伸ばされる才能は、次世代の日本を引っ張る原動力になるでしょう。
わたし自身、臨床美術に、大いに興味を持ちました。
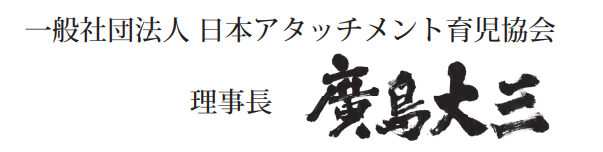
目次
- 開会のあいさつ
- 1日目:全国大会スキルアップ講座
- 『キッズマッサージ/アタッチメント・ジム 全面リニューアル』
- 2日目:育児セラピスト全国大会シンポジウム
- 東京家政大学 子ども支援学部 教授 / 特定非営利活動法人 日本臨床美術協会 副理事長
保坂 遊 先生 - 基調講演「アートと非認知能力の育ち」
- ▼ 優秀実践者発表
- 「志し」をカタチにして、保育園を立ち上げた保育士の物語
- ― 保育 部門 牧野 クルミさん
- 実家の「庭」からはじまった子育て支援の輪
- ― ダイバーシティ部門 衣川 由理さん
- ランチミーティング
- 恒例!お悩みスーパーバイズ2025