これからの子育ては、“リ・ペアレンティング”の時代
これからの子どもたちは、川の向こう側の世界を生きていく
わたしは、これまで25年以上のあいだ、仕事人(しごとじん)として、そして親として、「子育て・保育・教育」の世界に携わってきました。この間、ITという言葉が一般に知られるようになり、インターネット回線とWifiがあたりまえのインフラになり、スマートフォンがあまねく普及し、SNSは生活のたしなみになりました。さらにいま、ChatGPTに代表される生成AI技術の進化は、われわれの仕事を大きく変えようとしています。
この激動の時代を振り返ると、あらためて、その“変化”の大きさとスピードに圧倒されます。いまや、80歳を超えたわたしの母でさえ、ガラケーからスマホに持ち替え、LINEを使って写真のやり取りをしています。
だからといって、われわれは、果たして子ども世代と同じ世界を生きているのでしょうか。少なくとも、デジタルネイティブと言われる20代を境に、大きな川が流れているように思います。老年世代や、わたしのような50代の中年世代だけでなく、比較的若手の30代でさえ、(一部の天才をのぞいて)残念ながら川の向こうにはいません。そして、20代の若者世代や、これから大人になる子どもたちは、“川向こうの別世界”に生きている。そう考えた方が良さそうなのです。
“これまで”の価値観で、“これから”の子どもを育てることの危機
「子育て・保育・教育」に関して言えば、この数年はとくに、わたしは、ある種の危機感を覚えます。「このままではいけない」「いまから覚悟を持って備えなければいけない」という危機感です。
“川向こうの別世界”では、これまでの常識は通用しません。まったく別のルール、異なる法則が成立している世界だからです。フロイトやボウルビイも経験しなかったほどの「大きな転換」が起きています。

しかも問題なのは、相変わらず、川のこちら側の価値観で、親は子育てをして、保育士は保育をして、先生は教育にあ
たっていることです。子どもたちが、これから生きていく世界は、川の向こう側の世界なのに・・・危機感の正体は、この「ズレ」です。
たとえば、いま保育・教育の分野で注目の「非認知スキル」や、「探求学習」は、川の向こう側の価値観です。それは、わたしたち大人も知っていますし、理解しています。しかし、実際にやっていることは、川のこちら側の価値観のままなのです。
「非認知スキル」や「探求学習」は、言葉だけが踊っている
塾の広告では「お子さんの非認知スキルを育てます」と言いますが、やっていることは、テストで高い点を取る方法です。親もそれを塾に望んでいます。学校の探求学習の現場では、いつの間にか先生が作った模範テンプレートや、これまでの生徒の優秀な取り組みの二番煎じに置き換わり、どれだけその通りにできたかが評価されます。どちらも、これまでの“川のこちら側の価値観”です。
一部では、本来の意味においての「非認知スキル」を育てる試みがおこなわれるケースもあります。また「探求学習」においても、本来の好奇心や自由な発想による課題の取り組みを、真剣に進める先生もいます。しかしそれは、ほんの一部にすぎません。しかも、一貫してそうした環境に身を置けるケースは稀です。親はその価値さえ、理解できていないかもしれません。
残念ながら大半の大人は、“川のこちら側の価値観”です。そして、マジョリティに居ることで安心して、古いままで居続けます。これでは、これから生きていかなければいけない“川の向こう側の世界”で活躍できる子どもは育ちません。
これからの時代に活躍できる子どもの育て方
この「転換期」に、われわれ大人がやらなければならないのは、「自分が成功してきたやり方を子どもに押し付けない」、「自分が褒められたり叱られたりした価値観で、子どもを褒めたり叱ったりしない」ことです。そうした経験や価値観は、もはや「バイアス(偏見)」であり「邪魔」でしかありません。
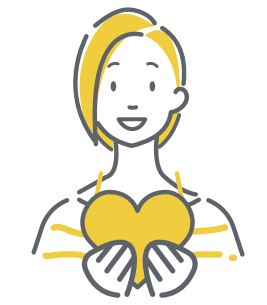
それを捨て去てれば、脳に空間(余地)ができます。この空間に、あらたに「川の向こうの価値観を入れる」ことができます。すると、これまでの自分の経験の評価が変わります。失敗と思っていたことは、本質で観ると“糧(かて)”になっていたりします。小さいころに叱られていた問題行動は、もしかしたら今の強みや得意を生む“才能の源泉”であったことを発見できるかもしれません。みずからがこれを実感できれば、このあたらしい価値観で子育てができるようになります。それこそが、“川の向こう側の世界”で活躍できる子どもを育てる子育てです。
古典に倣った「本質」に照らして、これまでの価値を再評価する
さらに、「川の向こうの価値観を入れる」というのは、どういうことかを考えてみましょう。一言で言えば、より抽象度の高い、あるいはレイヤーの高い価値観にアクセスするということです。そのときの指針となるのが「本質」です。
では、その「本質」をどうやって手に入れるのか?もっとも確実な方法は、古典をあたることです。心理学の古典といえば、フロイトです(もっと他にもいますが、ここでは一例として)。その派生にボウルビイやエリクソンがいます。哲学で言えば、アリストテレスです。
何が言いたいかというと、「100年前から言われていることで、100年後も同じように言われているであろうこと」の中に本質があるということです。
つまり「本質に照らして、価値を再評価する」ことです。たとえば、ある親が「テストの点数がよかったので褒めた」とします。このとき褒めた価値は「よい点数」です。この価値のレイヤーを順番に上げてみましょう。
「よい点数(結果)」を取るために
↓
「どう取り組んだか(過程)」
↓
「なんのためにそれをやったのか(動機)」
↓
「どうありたいのか(存在)」
「結果」よりも「過程」、「過程」よりも「動機」、「動機」よりも「存在」というように、価値観をどのレイヤーに置くかによって褒める機会も言葉も変わります。これは、テストの点に限らず、一事が万事に言えることです。
「リ・ペアレンティング」もっとも原始的な子育てに回帰する
もっとも原始的な子育てに回帰する。親には、そういうことが必要になると思うのです。
「リ・ペアレンティング」とでも言いましょうか。それは、「これまでのペアレンティング」に対して、「新しいペアレンティング」ということではありません。むしろ人間が、かつてあたりまえに行ってきた「より原始的で本質的なペアレンティング」の価値を見直して、現代に適応させたものです。

IQやテストの点数や知識の量のように数値で測れる能力(認知スキル)よりも、あきらめずに最後までや
り抜くような数値では測れない能力(非認知スキル)のほうが、より原始的で本質的です。決められた正解を、正確に導き出す「偏差値教育」よりも、答えのない問いに対して、探求心をもって深堀りして自分なりの答えを見つけだす「探求学習」のほうが、よりレイヤーの高い教育です。
「親の価値観」が変われば、子育て・保育・教育の世界線が変わる
決められた正解を、正確に導き出す能力において、われわれはAIに太刀打ちできません。そうした能力に依拠した仕事は早晩、AIに取って代わられます。一方で、答えのない問いに対して、自分なりの答えを見つけだす能力においては、人間の方が圧倒的に長けています。この領域は、AIが及ばない領域であり、人間にしかできない仕事です。
ならば、これからの時代に活躍するのは、間違いなく後者に長けた人材でしょう。そうした後者の能力を育てるカギは、間違いなく幼少期にあります。そのことは、古典心理学が、アタッチメントや自己肯定感、探求心、共感力と言った用語をもって、詳細に教えてくれています。そうなると、重要な役割を担うのは、親や保育士です。
しかし、残念ながら現状の保育や教育には、こうした後者の価値観は組み込まれていません。ようやく、非認知スキルや探求学習のように言葉だけが浸透し始めた段階です。加えて問題なのは、親の意識です。いまだに多くの親が子どもに求めるのは、IQや偏差値、テストの点数、知識の量といった前者の価値です。これまでが、うまくいっている親ほど、その傾向は強いでしょう。自分がその価値でうまくやってきた成功体験がありますから。
こうした親の価値観が変われば、子育てだけではなく、保育も教育も、一気に変わることでしょう。その先鞭をつけてくれている先生も、これまでは異端児でしたが、今度はリーダーになるでしょう。けっきょく大事なのは「親の価値観の転換」なのです。
「リ・ペアレンティング」によって、親と子の世界線が交わる
最初は、感度の高い少数の親が反応します。その人の子育ては、まわりの大勢にとって、風変わりに映るでしょう。ところが、そのうち、まわりで、この風変わりな子育てを参考にする人たちが現れます。そういう親が増えはじめると、学校で異端児だった先生は、相当数の親からの援護を得るようになります。すると、学校の空気が変わり、やがて方針も変わってゆきます。そして「学校がそう言うなら」と、マジョリティの親たちが変わりはじめます。
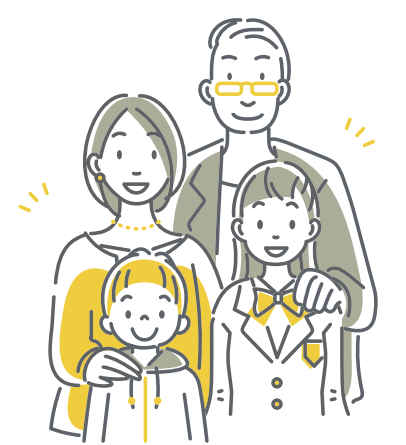
最終的には、川の向こう側の価値観が、子育てのあたりまえになります。ようやく親たちは、子どもがこれから
生きていく世界と同じ世界線に立って、子育てをするようになります。そうして、育った子どもは、激動と混沌の時代の中でも、それぞれの有能性を開花させ、みずから選んだ分野で活躍します。
それが、わたしの思い描く「リ・ペアレンティング」です。
一般社団法人日本アタッチメント育児協会
理事長 




